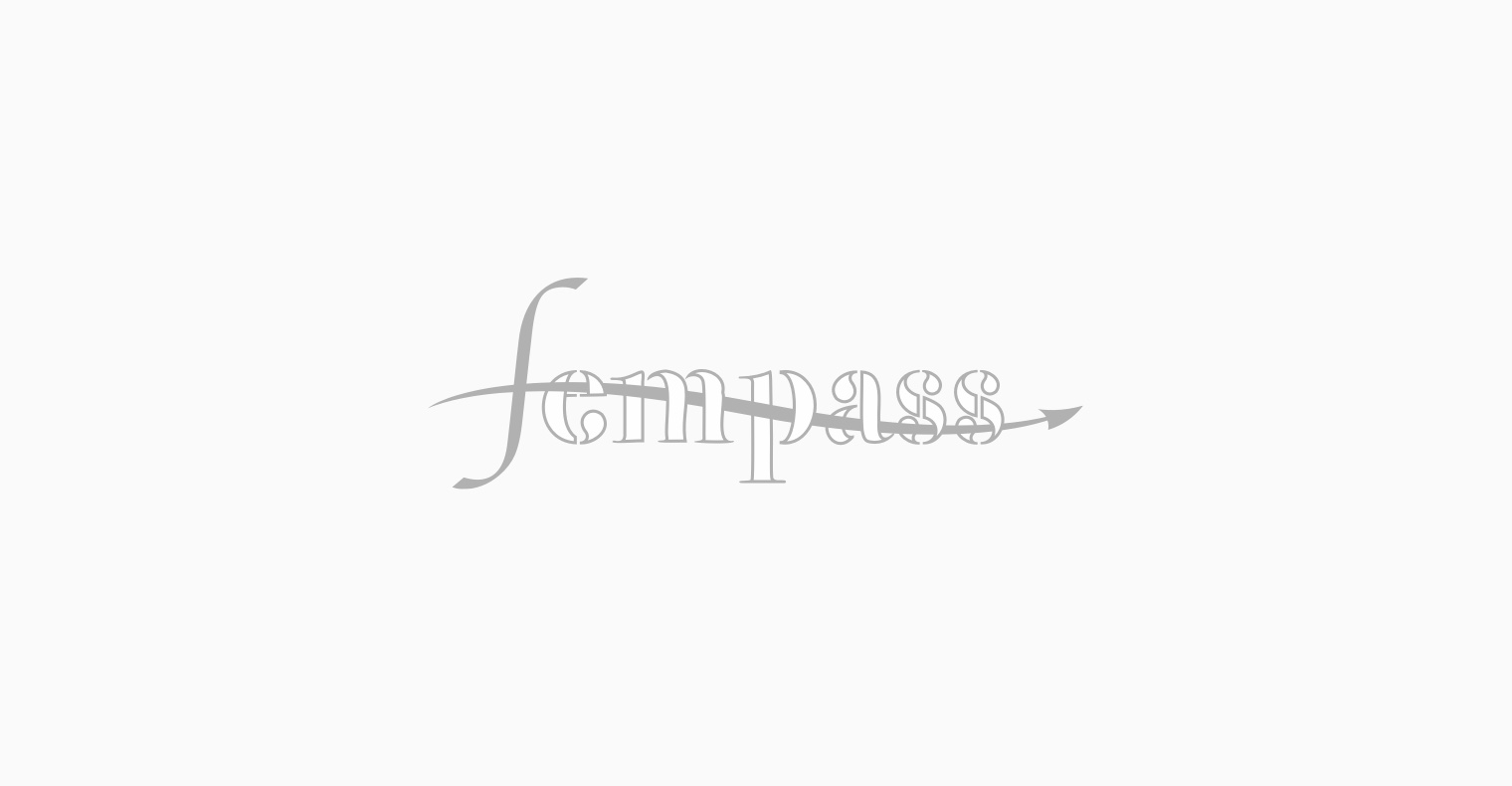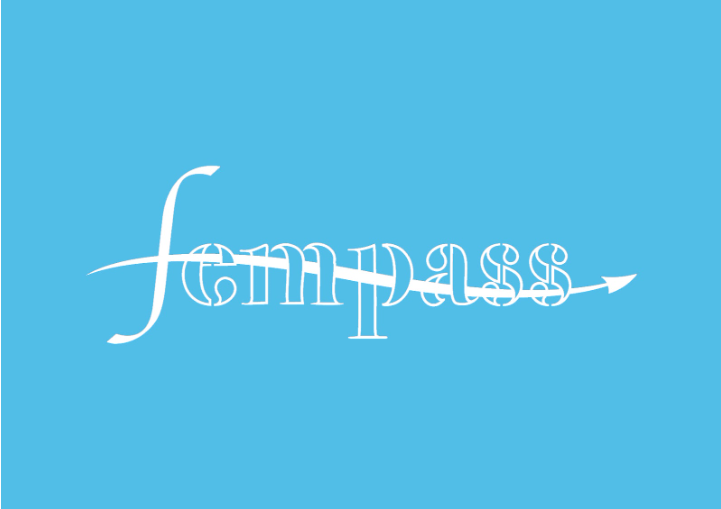あなたの夢を私に下さい
もうすぐ26歳を迎える。新卒で入社した今の会社もいつの間にかもう4年目。なんとなく受けてなんとなく入った保険の会社。お給料はそんなに高いわけじゃないけど、いろいろ手当とか保障はしっかりしている。毎日毎日どうでもいい数字をパソコンにカタカタカタカタ打ち込む。なんにも面白くないけど、頭を空っぽにしながらキーボードの上で踊るネイルを眺めるのは心地が良い。
だから別に、会社を辞める理由は特にない。
なんでもない毎日をなるべく疲れないように過ごしたい。
昔は週末になるとフェスとかライブなんかもよく行ってた。けど、そういうのって結構体力いるし次の日がしんどい。なんて考えると自分ももう若くないんだなっていやに分かる。
音楽は好き。軽音サークルに在籍していたこともある。新歓ライブでベースを弾いてた先輩がカッコよくて、ノリで入った。大学一年生の秋にはほとんど行かなくなったけど。
彼は四年生だったので、入学したての私にはすごく大人びて見えた。たばこを吸う横顔なんか、別の世界の知らない生き物みたいに輝いていた。
「さっきの、なんて音楽ですか。」
ライブが終わった後、おそるおそる聞くと「フジファブリック」と一言笑って答えてくれた。
先輩に憧れて私もギターを買ってみたけど、弾けるようになる前にやっぱり飽きてすぐ辞めた。
好奇心はある。新しいことが好き。だけどか、だからか、何かひとつのことがあんまり続かない。それほどやりたいことも、やる気もない。
やりたいこともないままいつの間にか大人になったから、そろそろ結婚したいなって思ってる。
*
「あさちゃん、今度の土曜、サークルの後輩と飲むことになったんだ。俺そんなに喋ったことないんだけど、マサって覚えてない?最近そいつのバンドがめちゃくちゃキテるらしくて。インスタでさ、なんか俺が今も音楽やってるの知ったみたいで、ぜひ飲みましょってDMきてさ。」
日曜日、13時。昼過ぎにのっそり起きたばかりの彼。私には目もくれず、ベッドでスマホをいじりながら話す彼はどこかご機嫌だった。いい歳して、目が隠れるほどある前髪のせいで彼の表情はほどんど見えない。
私はキッチンで洗い物をしながら少し思い返した。もちろん私だってマサなんか知らない。けど、昔から髪の長かった彼はベースが上手くて、仲間内では有名だった。私も彼に憧れる後輩の一人で、マサにとっても彼は一目置いてる先輩だったんだろう。
ばかみたい。何年前の話だよ。
「そうなんだ!きっとゆうくんに憧れてたんじゃない?」
「いやー、俺なんて別に他にやることなくてバンドやってるだけだし。
そんな大したもんじゃないって。」
そうだよ。大した事なんかないんだよ、バカヤロー。
「…それで土曜日、何時に帰ってくるの?」
「いや、わかんねーけど遅くはならんでしょ。連絡するよ。」
はーい、と適当に軽く返事したつもりだけど、上手くできていたかは分からない。
ゆうくん、土曜日は私の誕生日だよ。
*
ゆうくんのバンドは、ハッキリ言って全然売れていない。私の3つ上だから29歳。毎週ライブしてお小遣い程度のお金もらって、知り合いのバーのお手伝いしてまあギリギリレベル。
いつだろう。コロナが流行りだしてライブもバーも厳しくなって、ゆうくんはあの頃特にキツそうだった。だから、「割り勘にしようよ」って言ったあの日くらいから、なんでかいつも私が全部お金出してる。
一応インスタのフォロワーは6000人くらいいて、コアなファンも少しはいるみたい。週末は下北沢のライブハウスであれこれやってる。私も昔はよく観に行ってたけど、打ち上げに入れてもらったことは一度もない。「あさちゃんが来ても、別に楽しくないと思うよ」らしい。
軽音サークルで彼を見つけたのはずっと昔のことだ。憧れの先輩だった。
いつの間にかセックスして、いつの間にか一緒に居るようになって、いつの間にか一緒に住んでいた。
私達、お互いそれなりにたくさん遊んできたでしょう。もっといい男はいくらでもいる。商社マンとも医者とも経営者ともテレビで見たことある人とだって、寝た。
けど、なんでか私には結局ゆうくんがずっと一番なのだ。
そろそろ結婚したいお年頃。別に、ゆうくんとそうなりたいわけじゃないけど。
そんなの自分から言いたくもないし、今のままじゃ無理なのって自分が一番分かってる。
始まりが曖昧だと、終わり方もわからない。
*
「苺のタルトと、モンブランひとつ。」
こんなの自分で買って、何してるんだろう。誕生日が平日ならよかったのに。そしたらいつも通り会社に行くだけで済んだのに、今日が土曜日なせいだ。
「お祝い事ですか?メッセージカードとロウソクもつけましょうか」
まだ大学生くらいだろうに気の利くバイトさんだ。ハリのある白い肌がマスク越しにも眩しい。天使の輪っかがきれいな黒い髪は一度も染めたことがないのかもしれない。
「いえ、大丈夫です。彼の誕生日なんですけど、そういうの苦手だから。」
若くて可愛い女の子に、なに見栄なんか張ってるんだろう。自分のために自分でケーキ買ったっていいじゃん。
そんな自分に軽い苛立ちを覚えながら帰路に着いた。
自分の機嫌くらい、自分で取れる。家に着いたらLUSHの入浴剤でお風呂にゆっくり浸かって、お酒も少し飲んで、気になってたドラマの続きを観る。
日付が変わる前に帰ってきてくれなかったら、ゆうくんの好きなモンブランは私が食べよう。
*
AM5:01
ドアノブを勢いよくガチャガチャする音で目が覚めた。
ああ、そうだ。結局昨晩はゆうくん帰ってこなかったんだ。こんな時間なんだから起こさないように静かに帰ってきてよ。
「あさちゃんただいま~!」
まだお酒が抜けていない様子だ。彼はよろよろと歩きながらこちらに近寄り、私の布団に潜り込んできた。
「…お酒くさいよ。」
セミダブルベッドに二人って結構狭い。もともと一人でのんびり寝る用に買ったはずなのに、彼がうちに転がり込んでからはぐっすり眠れない。そもそも1Kに大人二人で住むってのが狭すぎるんだよ。
「飲み会楽しかった?」
嫌味のつもりで聞いてみた。
「ぼちぼちかな。」
だろうね、と喉から出かけた言葉を飲み込んだ。
自分より年下で売れてるバンドの子と話して、ちょっとは現実突きつけられたでしょ。自分に憧れてた子に追い越されてみじめな気持ちになったんでしょ。
なら朝まで飲むなよ。
彼に背を向けて再び眠ろうとしたけど、甘えるように後ろから抱きつかれた。
ゆうくんはぽつりぽつりと話し出した。
「俺、バンド辞めるよ。」
「ちゃんと就職するよ。」
「実はさ、この間昔のツレに一緒に働かないかって誘われたんだよ。話聞いてみたら意外と面白そうでさ。」
「俺がスーツ着るんだよ。笑っちゃうよな。」
「けど、結構似合ったりして。」
「…どう頑張ってももうこのまま変わらないのはさ、あさちゃんだって分かってるじゃん。」
「だからさ、結婚しよっか。」
えっ。
それはあまりに唐突で、反応に遅れた。
私いま、プロポーズされたよね。
バンド辞めて、結婚しよって。
彼は、さっきまで飲んでいたんだから、きっとまだ酔ってる。
だから、こんなこと言ってるの?
急に口内で唾液の分泌量が増えて心臓の動きが早くなった気がした。朝5時に起こされたばかりで頭はちゃんと働いていない。けど、いま、間違いなく現実だ。
ゆうくんは私の誕生日を忘れていることに、まだ気が付いていない。
*
「あのう、私、麻美真衣っていいます。」
「覚えてないですよね…。大学時代、一応同じ軽音サークルに入ってたんですけど。私全然行ってなかったし。」
「なんとなくここのライブハウス覗いてみたら、知ってる顔の人がいたからびっくりしちゃった。」
私たちが再会した日のことを思い出した。
「あー…、覚えてるよ!可愛い子入ったんだって思ってた。」
私は舞い上がった。憧れの先輩と再会して、ベースの重低音に鷲掴みにされて、先輩はやっぱりめちゃくちゃカッコよくて、私のことを可愛いと言ってくれて、これは運命だと確信した。私の中で腐っていた何かが溶けて、確かに動き始めたと思った。
思い返せば、彼はきっと私のことを覚えてはいなかった。
*
「そっか。バンド辞めちゃうんだ。結婚、かぁ。」
そっか。そんな、つまらないこと言うんだ。
私をちゃんと見てほしかった。大事にしてほしかった。打ち上げにも入れてほしかった。朝まで飲んでばかりなのもいやだった。バンドのボーカルが女なのも気に食わなかった。付き合おうってちゃんと言ってほしかった。誕生日も覚えていてほしかった。おめでとうって、一緒にケーキ食べたかった。
ベース弾いてる彼が好きで、小さなライブハウスだけど、ステージの上でキラキラしてる彼が好きで、全然ずっと売れてないけど、絶対成功するって息巻いてた彼が好きだった。
そんなゆうくんを応援している自分も好きだった。
あの頃のゆうくんはもういない。私もいない。
とっくに分かっていた。
本当はずっと欲しかった言葉なのに、ただそれは私の好きだったゆうくんがもういないことを再認識するだけの道具になってしまった。
涙がぽろぽろと流れて止まらなかったけど、泣いてる私を見た彼はそんなに嬉しいの、と私の横で寝ぼけながらのんきに笑っていた。
目を擦り、溜息をひとつついて彼に向き直る。
「ゆうくん、モンブランあるけど食べる?」
「え?今いらない。」
私の顔はきっとぐちゃぐちゃのままだ。
「そう。じゃあもう捨てておくね。」
沖みさき プロフィール
京の都に生まれ落ち、鴨川を眺め、高瀬川で溺れ、上京したのは二年前。ここでいうそれは東の都でございます。土地を移れど貫く自分、歳を取れど美しく。そうもうまくはいきません。
うまくいかないのもなんだかんだで楽しくて、今がよければそれでいい。そうも信じて24年、「将来」この二文字に攻撃されることが増えてきました。それでもなんだかんだで、最高にハッピーな今日を一生更新するもんねって、最初は皆思ってるもんね!!