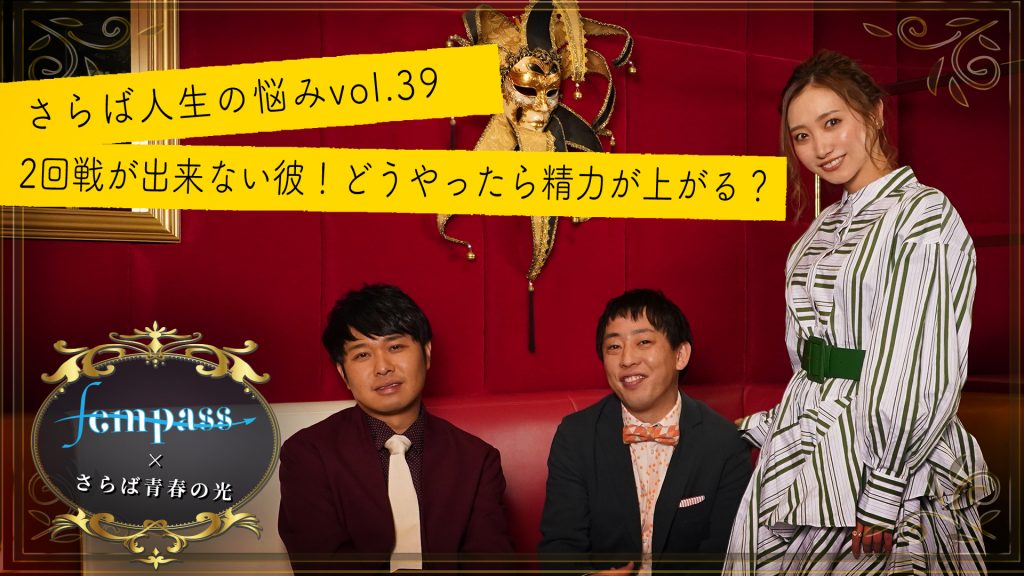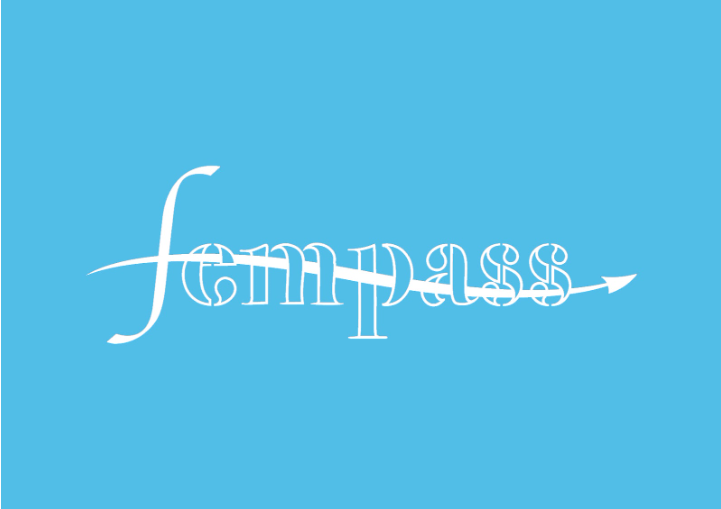先輩はいつも決まった時間にコーヒーを淹れる。
たまたま、うん、そう、たまたま、わたしも同じ時間にコーヒーを淹れる。
先輩が声をかけてくれた。
少し前に社内でとおった企画を褒めてくれた。
それだって先輩がアドバイスしてくれたのを参考に試してみたらいけただけなのに。
「おれはなにもしてないって」としずかに笑う先輩の目元の笑いジワを見て、
この人は誰にだってこうやって物腰柔らかく笑いかけて、ほどよく謙遜して、相手を気持ちよくさせる人なんだと思った。
自分には十分すぎるくらい、先輩との短い時間を過ごせて、
午後の仕事も頑張るか、と戻ろうとしたタイミングで、
「もう少し話さない?」と引き留められた。
その時のわたしは不自然ににやけすぎていなかったか、
やたらとテンションが上がりすぎていなかったか、
そんなことばかり気になって、まともに会話できていたのか思い出せない。
気付けば連絡先を交換して、退勤して夜になってもやりとりが続いていた。
隣で眠る、今日だって求めてくれない婚約者のことなんてどうでもよくなるくらい、通知がなるたび心が躍って。
こんな感覚になるのはいつぶりだろうと
冷静になるためになにかを無意味に数えてみたりして
そうしている合間にまた他愛のない会話の返事が来て、胸の奥がツンとなる。
先に寝てしまうのが惜しいと思いながら、通知を待っている間に眠って朝を迎えて
一番に見たスマホの通知は昨日のやりとりのまま続いている先輩からのメッセージで
このまま会話が続く喜びを感じながら顔を洗った。
鏡に映る自分はいつもより化粧ノリがいい気がした。
「おはよう」
「今日のランチ一緒にどう?」
私が送るより先に先輩からお誘いのメッセージが来ているのを見て飛び上がった。
いつもは私服として着るような、少しだけ色の明るいワンピースを選んだ。
ただランチに誘われただけなのに。
そういえば、彼とだって初めはただのデートすらうれしかったなと、ずいぶん昔のことを思い出したりした。
ただのランチだからやましいことはなにもない。
やましいことはなにもないのに、そう自分に言い聞かせて、
午前の仕事をいつもより早く終わらせて、化粧室でメイクの最終チェックをした。
先輩は想像していたよりも素敵な人だった。
優柔不断でランチメニューの2つを決めきれないでいたら「じゃあ二つ頼んでシェアにしようよ」とわたしが迷っていたどちらも選んでくれて、
「おれだってたまにはこっそりサボったりするよ」と、そんなわけないのに笑わせてくれて、
気付いたらわたしの恋愛の相談にまで乗ってくれて、
お手洗いに行っているうちにお会計まで済ませておいてくれて、
それが不自然じゃなくて流れるようにそうなっていて、
きっと普通のデートをしても、こうやってスマートにエスコートしてくれるんだ、と想像ができた。
多少女慣れしている人のほうが、わたしは好きなんだろうな、と自覚した。
婚約者も最初は優しく気遣ってくれるひとだったから。
今は変わってしまった婚約者の、昔の面影を先輩に映して、
違う人なのにあの頃の婚約者を重ねて
目が、心が、先輩を追ってしまう。
昼間の夢のような時間が、メッセージが続いていることで現実だったことを教えてくれる。
先輩とのやりとりを見返して眠りにつこうとしたとき、スマホが震えた。
目の前に広がるのは、先輩の名前が記された着信画面。
夜中になんだろう、と高鳴る気持ちを横で眠る婚約者に悟られないように、
でも気になって気になって胸が苦しくて、
こっそりベランダへ出る。
外はぼんやり曇って涼しくて、火照った体をちょうど冷ましてくれるような風が頬を撫でて逃げていく。
着信が切れちゃう前に出たくて
一息ついてから”応答”を押す。
耳にスマホをあてる。
「もしもし」と冷静を装って声を出す。
昼に聞いたばかりの先輩の声が、すこしだけ甘みと熱を帯びているような気がした。
目の前にいないから思う存分口元を緩める。
「いま何かしてた?」と聞かれる。
まさか、「婚約者が眠るベッドの中で先輩とのやりとりを見返してにやにやしていた」なんて白状はできなくて
「なにもしてなかったですよ?」と返す。
心の中に期待が募っていく感覚を覚えた。
「いまから、うちこない?」
あまりにストレートすぎる誘いなのに、断る理由が思いつかなかった。
先輩のその言葉が、このあとどういう展開になるのかの予想くらいつくのに
それが嫌だとは一ミリも思わなかった。
行くかどうか答える前に、こんな夜中に会うのならなにを着ていけばいいのかなんて考えていることが、先輩からの誘いの答えだと思った。
外に出ると雨が降っていた。
傘を取りに戻る時間すら惜しくて、そのままタクシーに乗り込んだ。
せっかく着替えたはずなのに、
自然を装って髪の毛にアイロンだって通したのに、
濡れるのもかまってられないくらい、はやく、先輩に会いたかった。
チャイムを押した。
鍵の開く音がする。
会って一言目、何を言えばいいかわからなかった。
「こんばんは」と口を動かすわたしを1秒見つめて、先輩は私の手をすぐ引いた。
「雨で濡れちゃいました」とか、「こんな夜中に外出ることないから新鮮です」とか、当たり障りない言葉を考えていたわたしの頭はもうすべてを投げ出して、
ただ黙って手を引く先輩についていくだけだった。
バッグを床に置いて、ジャケットをするりと脱がされて、ベッドへなだれ込む。
抑えきれない熱を感じて身を任せたのに、背中を支えてゆっくり寝かせてくれる。
こんな状況でもやさしさと気遣いが垣間見える。
きっとこれが先輩の本質なんだろう。
先輩は、何も言わなかった。
目で確認の合図が来た気がして、小さくうなずいた。
それからは、ただ、ただ、
わたしよりも高い体温を帯びる先輩を受け入れて
だんだんと先輩の熱がわたしの身体中を支配して
求められることが嬉しくて気持ちよくて
夢か現実かわからないふわふわした波に乗って
脱力して覆いかぶさってきている先輩のほどよい重さに安心を覚えた。
朝が来た。
もうずっとこの夜が続けばいいと願ってみたけど、すべての人間に平等に朝は来る。
「帰りたくないな」と、ぽつっとつぶやいた言葉を先輩が拾い上げる。
「じゃあ帰らなきゃいいじゃん」と煙草を吸いながらわたしに言う。
甘い煙に巻かれているだけなのはわかっていても、
それでも、
もうわたしの気持ちが婚約者に戻ることはないんだと気付いてしまった朝だった。
一度家へ帰ってシャワーを浴びた。
婚約者は休みで家にいた。
どこへ行っていたのか聞かれたけど、適当に濁した。
コーヒー淹れるけど飲む?と聞かれたけど断った。
もう求めてくれない婚約者に対して、わたしが「Yes」を言うことはなかった。
「おれたちって婚約してる意味あるのかな」
そう言ってきた婚約者の言葉が、
今のわたしには十分すぎるほど”最後”にふさわしいもので、
「もうその約束、忘れていいよ」と、丁寧にお返しするように、わたしからも最後の言葉を告げた。
うん、もういい。
わたしは求めてくれる人のもとへ行くから。
あなたが、わたしを抱かずにほかの女を抱いていたことくらい知ってる。
あなたが、わたしが出張へ行っている間にほかの女を家に連れ込んでいたことくらい知ってる。
あなたが、付き合いたての頃のようには戻らないことくらい知ってる。
あなたが、もうわたしを求める日なんてこないことくらい知ってる。
全部知ってる。
全部知ってて、だから悲しい。
キャリーケースに詰められるだけのものを詰めた。
なにか言いたげな婚約者と二人の思い出の詰まった部屋を置いて、
先輩の家へと向かった。
「しばらくうちにいなよ」と淹れてくれたコーヒーを受け取った。
先輩と二人でベランダから外を見た。
手巻きのたばこの匂いが先輩のにおいだと知った。
わたしを見つめる先輩が、喉まできたなにかを言いかけていた。
きっとそれはわたしが欲しい言葉だったけど、先輩は結局言ってくれなかった。
それでもいいと思った。
先輩と過ごしてしばらく経った。
人気者の先輩は、いつも誰かに呼ばれて夜に出かけることが多かった。
先輩の部屋で一人で過ごして一人で眠る。
忙しいだけで、わたしに飽きたわけではないよな、と嫌な想像がわいてくるのを
ベッドに染み付いた先輩の香りを嗅いで心を落ち着ける。
一緒にいる間は、まだ求めてくれている、まだ大丈夫。
無性に不安に駆られている間に、スマホが鳴った。
もうすでになつかしい、”元”婚約者からのメッセージだった。
「会って話がしたい」
彼を知っているからわかる。
わたしに戻ってきてほしいだけだ。
所有物を失ったさみしさを取り戻すためにあがこうとしているだけだ。
それでも、
「もしかしたら、また前みたいに戻れるのかな」
「また、わたしのこと求めてくれるようになるかな」
と淡い期待を少ししている自分がいることにも気付いた。
婚約者に求められずに、流れて先輩のもとへきた。
先輩からも求められないようになるのも時間の問題なのもうすうす気づいてる。
だったら、また婚約者のもとへ戻ってしまおうかと考えてしまう。
わたしのこの焦燥感が、いつか満たされる日は来るのだろうか。
ただ、だれかに大切にされたいだけなのに。
ただ、裏切られることを怖がらずにだれかを愛したいだけなのに。
先輩でなきゃいけない理由なんてなかった。
ただ、その瞬間にわたしを宝物のように扱ってくれそうだったのがたまたま先輩なだけだった。
正直、誰でもよかったんだ。
求めてくれるなら、誰でもよかった。