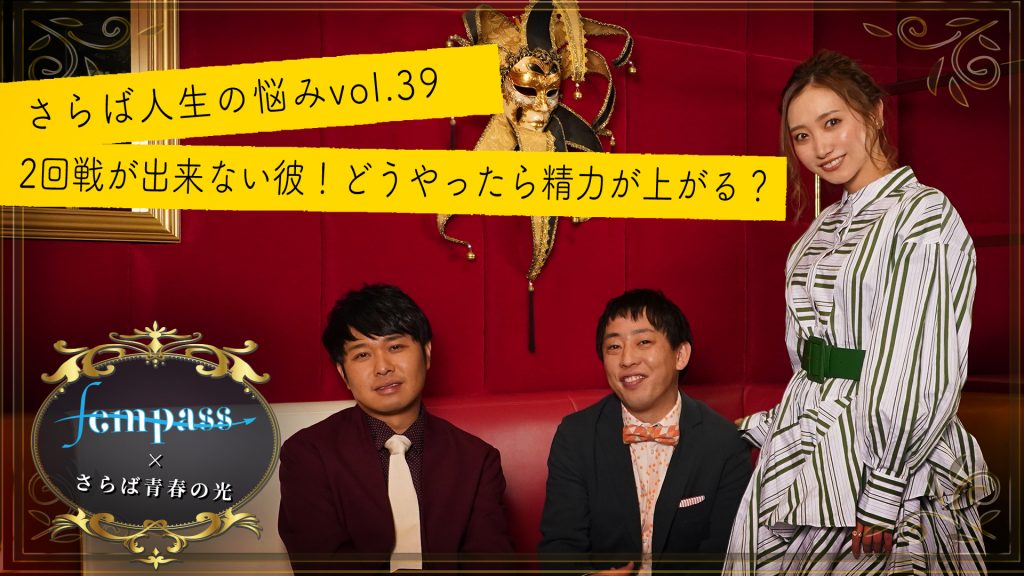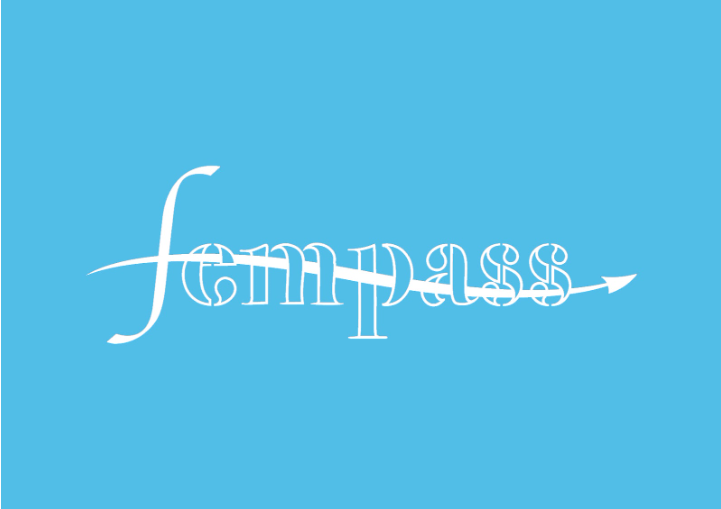きみの眼差しが好きだった。
たっぷりの砂糖を混ぜた生クリームよりも甘い、とろけるような微笑み。
きっと彼女は、口づけた瞬間に潰えてしまう──淡雪から生まれた、罪深いスイーツ。
独占して、束縛して、他の誰にも触らせたくなかった。
そんなぼくのわがままを、きみは咎めない。
抱きしめたら潰れてしまいそうな柔らかい体と、吸いつくような白い肌が、ぼくの心を惑わせる。
花に埋もれた白桃の膨らみも、青いシーツに伸びるしなやかな脚も、ぜんぶ、なにもかも、独り占めしたい。
ぼくの自分勝手な願いに、彼女は「いいよ」とうなずいてくれた。
身の丈に合わない願いを抱いた愚かな男と、それを受け入れてくれる慈愛の天使。
ふたりきりの逃避行。
ヘンゼルとグレーテルが置いたパンのかけらを追いかけて──辿り着いた先は、桃色のネオンが輝くお菓子の家。
テーブルのビスケットを摘んだ彼女が「魔女はいないね」と嘯(うそぶ)いた。