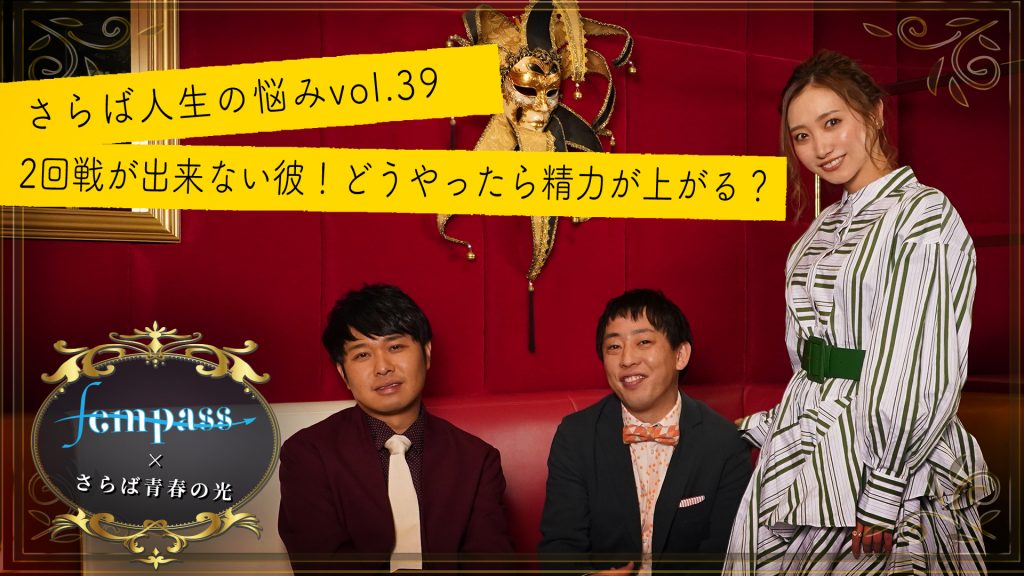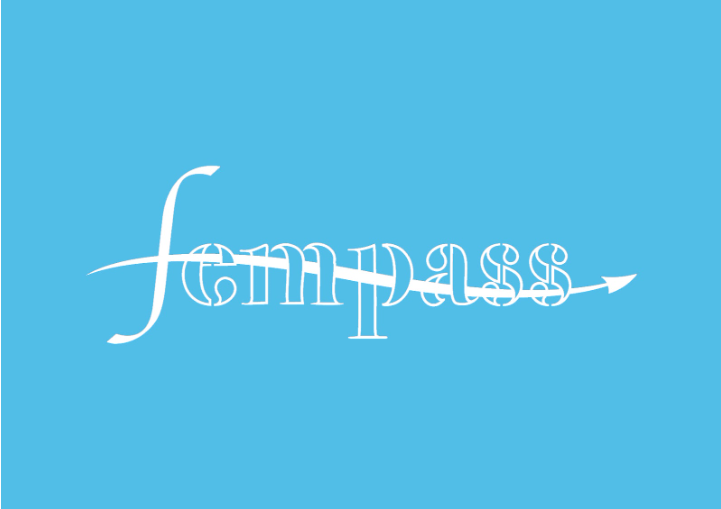真っ赤なソファーでくつろぐ姿は、まるでショートケーキ。
そんな戯れの妄想にも、きみは「私がクリームとスポンジなら、主役の苺はどこ?」なんて可笑しそうに囀(さえず)ってくれる。
ぼくが思わずその唇を見つめると、グミを咥えた彼女は悪戯っぽく「キスがしたいの?」と囁いた。
ベッドの上で遊ぶ彼女を眺めながら、ふと不安に駆られる。
きみの翼を、ぼくという鎖が縛っているだけなんじゃないかって。
これは蝶の夢。
目覚めのあと──きっと彼女は、いまより輝ける場所へ飛んでいけるだろう。
独りよがりの嫉妬だ。
それでも彼女を手放したくなくて、ぼくは「さようなら」を口にできない。
豊麗なマシュマロの丘を、飴細工のように滑らかな稜線を──。
そのすべてを、ぼくだけのものにしたかった。
ふいに身を乗り出してきた彼女が「どうしたの?」と、こちらを覗き込む。
黙り込んだぼくの首に、きみは迷いなく手をかけた。
「私、ずっといっしょにいるよ」
その言葉だけで、救われる。
ドリンクを手にした彼女が、「これは魔女のジュース」と微笑んだ。
それを飲んだあと、最初に見た相手と、永遠に離れることができなくなるという。
ぼくが「先に飲んでいい?」と尋ねると、きみは「ダメ」と首を振った。
「あなたを好きになったのは、私のほうが先だから」
物語の終わりに、ヘンゼルとグレーテルは家に帰る。
お菓子の家がどうなったのか、グリム童話は語らない。
その続きを、ぼくと彼女で紡いでいこう。
きみの視線が好きだった。
ふわふわのスフレにかけたチョコレートよりも甘い、蠱惑(こわく)の微笑。
きっと彼女は、口づけのあとも胸を満たす──ぼくを射止めた、恋のスイーツ。